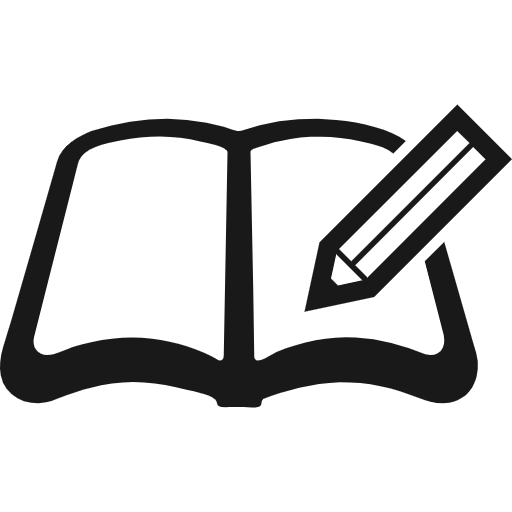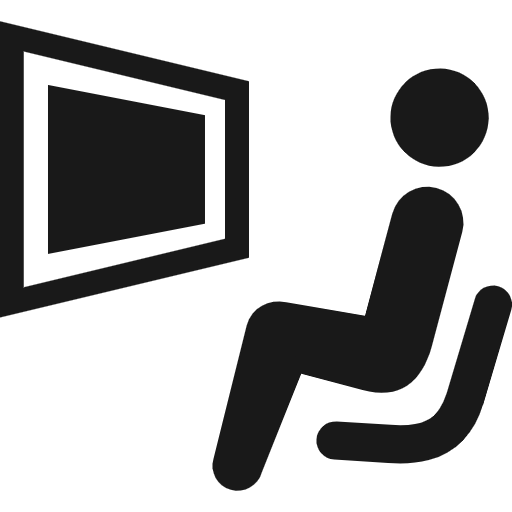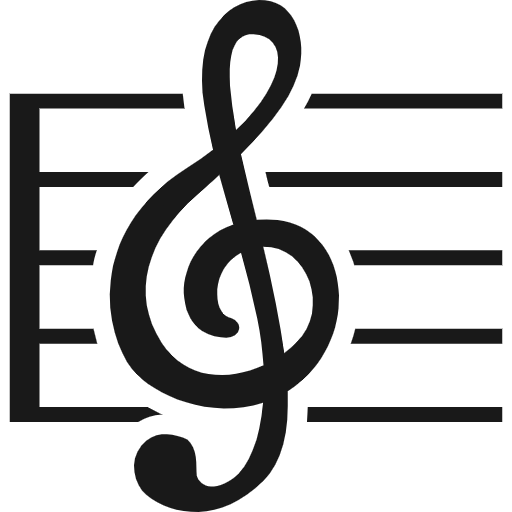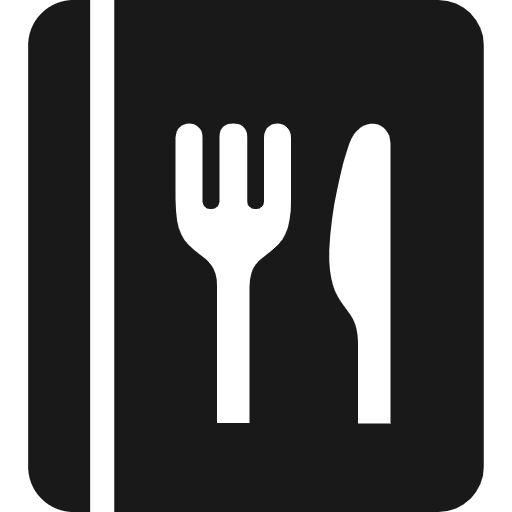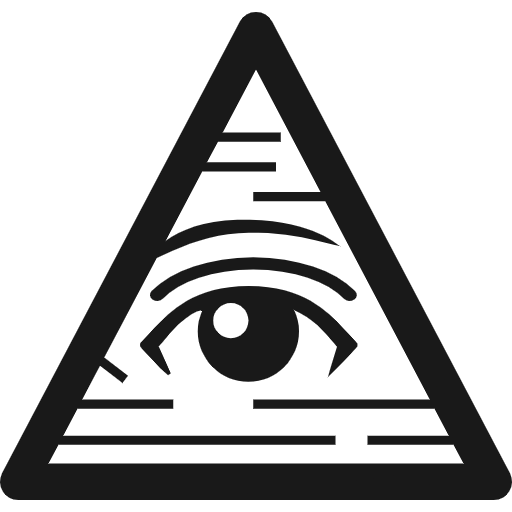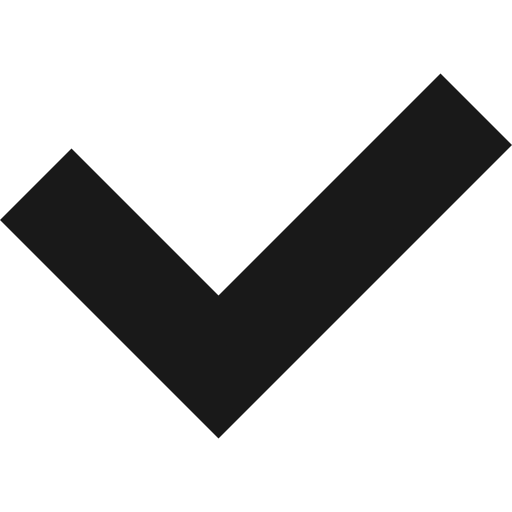子供の頃、ある疑問が頭に浮かび母に聞いたことがあった。
「“七転び八起き” って知ってる?」。
すると、母は、
「何度転んでも起き上がること」
と、そのまんまの回答をした。
「七転び八起き」とは、
何度失敗しても屈することなく立ち上がることのたとえ。また、人の世の浮き沈みの激しいことのたとえ。(コトバンク「七転び八起き」より)
母の回答は、当たらずも遠からじってことにしといてあげよう。
そして、わたしが、
「七回転んだら、起きるのは七回だよね。なんで八回なの?」
と聞くと、母は黙り込んでしまった。
「・・・・・・」
「ねえ」
「うるさい、おほほほほ・・・」
( ̄◇ ̄;)
と、まぁいつもの “結” のない親子の会話だった。「七転び八起き」の解説については、文末のリンクをご覧ください。
さて、「七転び八起き」と同じように、最近ふと疑問に思ったことがあった。それがタイトルの川柳で意味は、
居候は、他家に世話になっている手前、食事の際も遠慮がちになる。(コトバンク「居候三杯目にはそっと出し」より)
はて? なんで二杯目じゃなくて三杯目なんだ? 居候なら二杯目でもおかわりし辛いだろと思ったのだ。
適当な回答をするお手頃の話し相手だった母はもういないし、妻に聞いたところで、
「しらん」
と、一蹴されるのは必至。
ネットで「居候三杯目にはそっと出し」を検索しても意味だけで、なんで二杯目でないのかヒットしない。
ならばと、「居候── なんで二杯目でないの」で検索したら、『「鰻丼」を食べる人が知らない“昔の驚きのタブー”』なるサイトがヒットした。
「鰻丼」と「居候──」の関連性は分からなかったが、とりあえずこのサイトの記事を読んだら目から鱗だった。冒頭、
- 江戸時代は、鰻丼は鰻飯(うなぎめし)と呼ばれていた
- 江戸時代は、頭を取り除いた長さが3~4寸(約9~12センチ)という、ドジョウのように小さな子供のウナギの蒲焼が使われていた
- 江戸時代の丼(どんぶり)は小さく、何杯もおかわりして食べるのが鰻飯だった
と、鰻の蒲焼の話ではじまり、『昔の丼鉢はとても小さかった』こと、『江戸時代にどんぶりものが普及しなかった理由』が説明されていた。
- 日本にはかつて、「一膳飯」という非常に強力なタブーが存在した
- かつての日本では、葬式の時に一杯だけご飯を食べて死者と別れるという儀式が広範囲に行われていた
- そのために、普段の食事においておかわりをせずに一杯だけのご飯で済ますことは、葬式を連想させる行為として非常に忌み嫌われていた
- 一杯で満腹にさせる丼も、一膳飯というタブーに触れる不吉な食べ物として忌み嫌われていた
また、『牛丼の戦前史(近代食文化研究所 著)』には、太平洋戦争末期に作られた『軍隊小唄』1番の歌詞を紹介し、
いやじゃありませんか軍隊は
カネのおわんに竹の箸
仏様でもあるまいし
一膳飯とは情けなや
と、一膳飯を忌み嫌う兵士もいたことを記している。
よって、居候も「一膳飯」のタブーを回避する義務として、二杯目は堂々とおかわりができ、「居候三杯目にはそっと出し」だったのである。
なお、記事は、明治時代中頃に鰻飯の「大丼(現在の大きさの丼)」が現れ、人々が一膳飯のタブーから解放され、丼に慣れていったこと、『鰻飯から鰻丼への変化』『大人のウナギを使う鰻丼が普及』の説明で締めくくっている。興味がある人は文末のリンクをご覧ください。
ところで、江戸時代の元禄期(1688~1704年)以降に1日2食から3食に変わったが、江戸ではひとりが1日5〜6合のごはんを食べたという。米1合は150gで炊き上がると300〜350gになるので、1日1.5〜2.1kgのごはんを食べていたことになる。昔の人はごはんを何杯もおかわりしたと思うが、主食が米(ごはん)で一汁一菜でしたから自ずとそうなったのでしょう。
今は主食にパン、麺類も加わり、テーブルに並ぶ料理も豊富になったことでしょうから、ごはんを何杯も食べる人は少なくなり、1杯で済ます人が多くなったのかな。
わたしは子供の頃、茶碗のごはんはおかわり1回の2杯で十分だった。稀に3杯目になると、母から、
「そんなに食べるとお腹壊すわよ」
と、言われたし、一膳だけだと、
「具合でも悪いの?」
と、心配されたり、
「夕方にかっぱえびせん一袋食べるからよ」
と、叱られたものだった。
つまり、昭和一桁生まれの母には、一膳飯のタブーは持ち合わせていないことになり、大正一桁生まれの父からも、「昔は一膳飯は忌み嫌われた」と、言われたことが、ただの一度もなかった。つまるところ、大正期には多くの人々が丼(大丼)に慣れ、一膳飯が暗黙の了解になっていたのだろう。